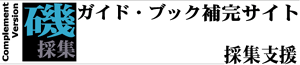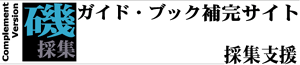経験から言えること
|
|
1) |
魚の写真は採集ものだけでなく、水中撮影は勿論のこと、釣り、定置網もの、漂着もの、市場、店舗などでも得られる。魚が目に映ったらチェックを。
|
|
| |
2) |
水槽で魚の写真を撮る場合には背景にも気を配る。
採集地に近い情景を用意すると生態写真らしくなる。温帯種なのに背景には熱帯の生物類が・・・というのは避けたい。また人工物の写りこみというのも避けたい。
|
|
| |
3) |
水深はそれほど正確でなくてもよいので、自分の身体をメジャーがわりに使う。一度ご自身の各部位を測ってみてはいかが。膝まで何cm、股下何cm など。
|
|
| |
4) |
全長は、魚へのストレスをできるだけ避けるために、魚とスケールを同時に写し込んで、パソコンで測るという方法をとっている。(画像はクリックで拡大)
|
|

|
|
5) |
管理番号は、自分のパソコン内での画像NO.で、「あの写真はどれだっけ?」といった場合の迷子対策。
保存枚数が多くなってくると後で1枚1枚照合するのはとっても大変な作業となってしまう。デジタルカメラの場合、自動的に付けられる画像 No.のままでよい。
|
|
その他の記録
|
| |
毎年毎年お金と時間を費やして採集に行くのならば、採集魚以外でも何か記録できるものがあるのではないか?という考え方です。
例えば、足繁く通う場所の生物相を記録し把握してみるとか、ある生物に着目して観察を記録し続けるなど、もしかしたら面白い結果がでるかもしれません。
|
|
| (ページ編集/文 江藤幹夫) |
|